アニメスタジオクロニクル No.9 STUDIO4℃ 田中栄子(代表取締役社長 / プロデューサー)
アニメ制作会社の社長やスタッフに、自社の歴史やこれまで手がけてきた作品について語ってもらう連載「アニメスタジオクロニクル」。多くの制作会社がひしめく現在のアニメ業界で、各社がどんな意図のもとで誕生し、いかにして独自性を磨いてきたのか。会社を代表する人物に、自身の経験とともに社の歴史を振り返ってもらうことで、各社の個性や強み、特色などに迫る。第9回に登場してもらったのは、STUDIO4℃の田中栄子氏。本連載では初登場となる女性の代表取締役社長だ。「自分たちが好きな作品を作ってきた」と語る田中氏に、独自のスタンスでアニメ制作を続けてきたSTUDIO4℃の歴史や、最新作「火の鳥」への思いを語ってもらった。
取材・文 / はるのおと 撮影 / 武田真和
STUDIO4℃はクリエイターありきの会社
独立したアニメ製作スタジオでは珍しい、女性のトップである田中栄子氏。彼女がアニメ業界で働き始めた1980年代は、女性にとって相当に過酷な現場だったようだ。まずはSTUDIO4℃設立までのキャリアを振り返ってもらった。
「大学卒業後にまず広告代理店に入社し、その後に縁があって日本アニメーションに入りまして、企画を経てプロデューサーから現場入りしました。その頃は女性の制作なんて1人もいない状況でしたけど、プロデューサーをしながら制作進行もしなければ納品が間に合わないので、なんでもする。現場の叩き上げです。とにかく忙しいんです。1日に28時間あっても足りないくらい。1年400日くらいの感覚で走りきるみたいな仕事の仕方でしたね。通常、女性は結婚で寿退社。会社ではお茶汲み。現場に来れば女性は男性以上に働いて一人前という時代です。当時は労基も厳しくなかったので、そんな働き方が業界というか、これはアニメ界だから特別ではなく世間での常識でしたね。
当時会社の方針で退職勧告もあって、自分の働き方には限界があると思い知らされた頃、ジブリから要請があって、『納品に追われ続けるシリーズではなく、劇場作品なら少しは時間に余裕ができるだろう』とスタジオジブリに籍を置きました。そこで『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』のラインプロデューサーをしました。ところが仕事に楽とかはないんですよね。結果、時間的にも精神的にも、責任的にも大変になった(笑)。緊張が納品ごとに短期で回収されないんです。年々続く、もう体が持たない。それでこの業界から足を洗おうと決心して、『いっそ、自分が働きやすいよう自分で会社を起こそう』という思いもありSTUDIO4℃を設立したんです」
STUDIO4℃の設立には、彼女のそんな思いのほかにもいろんな背景があった。同社サイトには「スタジオ4℃はこうして出来た!!」と題されたコラムも掲載されている。田中氏はこの小文を「確かに嘘は書いていないけど、ずいぶん冗談めかして面白おかしく書いています(笑)」と語るが、実際はどんな経緯があったのだろうか。
「もともと、自分たちで、自分たちの作りたい作品創りをしたいというクリエイターたちの願望があったんです。小規模なスタジオがポコポコできていた時代でもあります。当時は映画はたまにしか作られなくて、作品ごとにクリエイターは集められて、解散となります。映画に参加したいために、在籍していたTVシリーズ中心の会社を退職すると、元には戻れない。そのため“劇場フリー”という実力のあるクリエイターたちがけっこういました。でも、クリエイター個々人では大規模な作品を作ったり、そもそも請け負ったりするのはなかなか難しい。だから社会的な信用やビジネス面の契約などを含めてしっかりサポートするための会社を設立するよう、彼らと交流のあった私に相談がきました。
だからSTUDIO4℃は会社のための会社ではなく、クリエイターのための会社です。劇場アニメに参加する人もいれば、アーティストのMVを手がける人もいる。それぞれが好きなことをして働ける場としてスタートしたんです。私も設立当初は『あんなに大変な思いをしたから、もうアニメはできない。プロデューサーはしない!』と誓ってライターをやっていましたし。設立から30年近く経ちましたけど、今もそういったクリエイターが主体という意識は変わっていません」
GLAY「サバイバル」のミュージックビデオ。監督を当時STUDIO4℃に在籍していた森本晃司が手がけた。
ターニングポイントとなったデビュー作「MEMORIES」、その後は余生!?
こうして設立されたSTUDIO4℃にとって初の本格的な自社作品が、1995年に公開された劇場アニメ「MEMORIES」だ。「AKIRA」で知られるマンガ家・大友克洋が製作総指揮を行った3話構成のオムニバス作品で、2話分をSTUDIO4℃が制作、劇場としての作品の完成・納品も田中氏がプロデュースしている。田中氏は、同作がSTUDIO4℃にとって最大のターニングポイントだったと振り返る。
「それまでバラバラに好きなことをやっていたSTUDIO4℃のクリエイターがまとまって仕事をした初めての作品でした。しかも制作中の大友さんに『どうせやるなら世界一を目指そうぜ』という気概があったんです。その姿を見て自分たちに何ができるか考えるようになり、『(STUDIO4℃がある)吉祥寺から世界を目指そう』という思いを抱き始めました。
当時、すでに歴史も実力もあるアニメスタジオがたくさんありました。だから普通に仕事をしているだけでは、我々のような小さな会社はただの下請けで終わってしまう。でも大友さんに刺激を受けて『MEMORIES』からは世界に打って出るような姿勢を持つようになったし、基本的には下請けではなく元請けで仕事をするようにしました。
そもそも下請け根性というか、何かに屈しながら嫌々作るようではクオリティの高い作品にならないでしょう。まあ、私が誰かの言うこと(田中注:理不尽な命令)を素直に聞くようなタイプでないこともありますけど(笑)。やっぱりクリエイターが発信したいものを作るという発想を、改めてスタッフ全体で持つようになったのもこの頃です」
その後のSTUDIO4℃の基本姿勢を作るきっかけとなった「MEMORIES」は、プロデュースを手がけた田中氏個人にとっても大きな転換点となった。彼女は壮絶なエピソードを語りながら「『MEMORIES』以降は余生」だと笑う。
「『トトロ』で10円ハゲが2つできて、『魔女の宅急便』で胃潰瘍になって血を吐いて。ずっと『もうアニメのプロデューサーは絶対にやらないよ』と言っていたんですけど、結局『MEMORIES』もやることになって(笑)。その制作中に心筋梗塞で集中治療室に運ばれ、5分間ほど心停止したんです。しかも2回。それでも現場に復帰して納品したんですけどね。そのときに『死ぬときはあの世に何も持っていけないんだな』と実感し、お金なんかあってもしょうがないと思うようになりました。だから『MEMORIES』で死んでからは私にとって余生なんですよ」
「死んでも納品する」。そんなすさまじい体験を実際に行った田中氏に、なぜ必死に作品を完成させ、さらに同じように作品作りを続けるのか聞いてみた。
「そりゃあ、一度作品を作るとなったからには納品しなくちゃいけないので(笑)。私は納品についての責任感は強いんです。でも会社についてはそうではなくって。もともと4℃はクリエイターが作りたいものを作るための会社で、仕事がなくなったら終わりでけっこうですというスタンスです。実際に『MEMORIES』を作り終えて、あとは前から手がけてた片渕須直監督の『アリーテ姫』を作ったら会社を畳もうと思っていました。でもそうこうしているうちにいろんな仕事の話が舞い込んできて、その中には面白そうなものも多かった。そんなふうに自分たちが作りたくなる、面白いと感じる作品と常に出会えてきたので、今もSTUDIO4℃は続いています」
「会社をこれ以上大きくしない」という決意
さらに田中氏は、STUDIO4℃にとっての次のターニングポイントとして、作品ではなくとある出来事を挙げた。2011年に行われた社屋の移転だ。これは外部からは単なる吉祥寺内での移動に見えるが、田中氏にとっては大きな意味を持っていた。
「それまでは吉祥寺の駅に近い大きなビルの2フロアを借りていました。いつでも会社を終えられるよう賃貸だったんですけど(笑)。でも2011年に駅から少し離れた場所にあるビルを買い取って引っ越したんです。それは『これ以上は大きい会社になりません』という覚悟をしたタイミングでもありました。
その直前には『ベルセルク 黄金時代篇』の映画3部作や、アメリカのTVシリーズの『サンダーキャッツ』、ゲーム内のアニメ、フランスとの合作『ムタフカズ』、新作映画のプリプロとたくさんの仕事を並行していたんですけど、もうボロボロです。それにやればやるほど儲かるかというとそうではないんですよ。100やって1儲かるとして、1000をやったからと言って10儲かるかというとそうではなく、結局儲けはそこそこで。だから会社を大きくしていろいろと忙しく作るより、丁寧に作品を作ろうと決意したんです。
もちろん儲けたくないわけではないんですよ(笑)。でも、それによって作品の作り方や経営方針のプライオリティが変わるのは違うというか。会社を継続するためには難しいところではあるんですけどね。だからいろんな方に『STUDIO4℃はよく続いているね』『アニメ業界の七不思議だ』なんて言われます(笑)」
1993年の設立時、STUDIO4℃に所属していた社員は10人程度。その後、規模は拡大していったが、事務所の移転前後からは40~50人くらいで維持しているという。しかし規模は変わらずとも、変化は起き続けているそうだ。
「例えば大学を卒業してからうちでずっと監督を目指しながら仕事をしていた廣田裕介くんが『映画 えんとつ町のプペル』で初映画監督を務めたし、もう2~3人ほど監督デビューをする予定があります。あとは成長して巣立ったスタッフも、外の会社でがんばっているし、うちの作品に参加してくれたりして。そういうふうにクリエイターや制作が育って、彼らが作品を作るという流れができたのはうれしいですね」
そんな新たなサイクルに入っているSTUDIO4℃。田中氏は近年の作品で特に印象深い作品として、「海獣の子供」を挙げた。2019年に公開された、五十嵐大介によるマンガを原作とするファンタジー作品だ。
「『海獣の子供』はもう大変でしたね……。最初のテストカット映像が上がったときに『こんな大変なことやるの!?』と驚きました。『こんなに描いていたら作画が終わらないよ』とメインスタッフに言ったんですけど、『それでもやる』って。それで長期戦になるだろうからお金もたくさん積まなくちゃいけないと覚悟したのを覚えています(笑)。
でもクリエイターががんばって粘ったおかげで『ついに作画を極めましたね』みたいな評価をいただいたりして。私も、今のアニメーターが表現できる作画としては頂点の1つになったと思うし、誇れる作品になりました。この作品での3Dの使い方も秀逸です」
劇場アニメを中心に作っていることもあり、STUDIO4℃は寡作と言ってもいいだろう。しかし作品の評価は軒並み高く、特にクオリティの高い作画は定評のあるところだ。
「やっぱり作画はアニメ制作の中でも注力しているところです。あればかりは才能がないとできません。3DCGでなんとなくうまく動かすこともできるし、それも才能が必要なことだとは思いますけど、絵をうまく描くのはやっぱり特別です。普通の人が普通に何かしていることを絵にすることって本当に難しい。例えば『ご飯を食べて美味しい』というあの感じを絵で表現できるアニメーターって、日本が誇る財産だと思いますよ。
もちろん手描き作画だけでなく、3DCGも力をつけました。『映画 えんとつ町のプペル』ではキャラクターだけでなく背景やプロップまでフル3Dですけど、いい作品になりましたし。あれは『ベルセルク 黄金時代篇』のときに甲冑を着た兵士が大量に出てくるシーンなどで培った3D技術が活きました。そういうふうに前の作品でチャレンジしたことを次の作品に活かすことが多いんです。特にMVや短編の制作で挑戦したりもしましたけど。今後も、技術面もそうだし、表現力においても常に新しいものを目指したいですね」
「MEMORIES」から続く系譜の最新作「火の鳥」
設立から35年ほどが経ったSTUDIO4℃。そんなアニメスタジオの最新作が劇場公開される。手塚治虫の「火の鳥 望郷編」を原作とするアニメで、すでにディズニープラスでは「火の鳥 エデンの宙」が独占配信済み。それとはエンディングが異なる「火の鳥 エデンの花」の上映が11月3日に始まった。
「STUDIO4℃には、うちが作ったオリジナル企画と、外部から制作の依頼を受けて共同で作るという大きく分けて2種類の作品があります。『火の鳥』は前者で、『MEMORIES』から始まって『アリーテ姫』『マインドゲーム』『鉄コン筋クリート』『海獣の子供』と続く系譜の最新作という位置づけです。
今回は私が作りたくてスタートさせた企画です。あるときにふと『手塚治虫という日本が世界に誇る巨匠の作品のアニメを、なぜうちが作ったことがないんだろう』と思い、手塚プロダクションに作らせてほしいとお願いをしに行きました。そして子供の頃から読んでいた『火の鳥』の、これまでアニメ化されていない『望郷編』をアニメ化させていただくことになったんです。
その後の具体的な企画を作る段階で、エンディングが異なる2バージョンを制作するという構想になりました。『望郷編』って朝日ソノラマ版や少女クラブ版、COM版、角川書店版、講談社版のようにかなりたくさんあって、それぞれ登場人物や結末が違うんです。だからアニメでも同じようなことをすると面白いんじゃないかなと思ったんです」
田中氏にとって待望の作品となる「火の鳥 エデンの宙」「火の鳥 エデンの花」だが、その制作はいつも以上に大変だったようだ。
「今回の『望郷編』のアニメ化は、実は7年前から始まっています。シナリオ段階で難航しました。原作の『火の鳥』は全12巻あって、そのうちの未来を描いた『宇宙編』や『未来編』『復活編』などからもエピソードを引っ張ってきています。壮大なSF大冒険譚です。そもそも今『火の鳥』をアニメ化するなら人間の深い欲望が地球の崩壊につながるといった手塚治虫氏の強いメッセージは外せないけど、それを全面に出す「だけ」では面白くならないし……。作品中に難しい表現、近親相姦やカニバリズムもあるし……。
本当に紆余曲折あり、西見祥示郎監督は大変だったと思います。エデン17という移民星はなぜ滅びたんだとか、空気は薄いのかとか、SFの設定にも苦労してます。絵コンテでも映像にこだわりの強い監督が『こうしたら面白いんじゃないか』などといろいろと工夫してまして、あちこちに監督のこだわりが見えます。宮沢りえさんや豪華声優もこの作品の力になってくれました。特に音響、SEと音楽もとてもいいと思うので映画館でじっくり浸りながら観てほしいです。Dolby Atmosにも対応しているので、ぜひ映画館の真っ暗闇の中で、目でも、耳でも、皮膚でも楽しんでください。自分の知らなかった感性みたいなものが刺激されるというか……。映画館特有の、ああいう体験をしてほしいんですよ」
STUDIO4℃がなかった30年を想像したら……
2016年に公開された「君の名は。」以降、毎年のように興行収入が100億円を超えるメガヒット作が生まれる劇場アニメ業界。このバブルのような現状を、田中氏は大きく歓迎する。
「昔から宮崎駿さんとか押井守さんがメガヒットを飛ばす横で、私たちは規模こそ大きくないけど好きなものを作るというスタンスだったので、基本的にはあまり変わっていないというか(笑)。業界が盛り上がってくれるほど、うちへの注目も増えるからありがたいです。世間から『アニメが儲かる』というふうに捉えられたおかげで、私たちも作りやすくなったところもありますし。
ただ、そういう『儲かる』というか、売れると太鼓判を押された作品ばかりになる可能性もありますよね。ビジネスなのでそれは仕方ないことですけど。そういうメジャー化やエンタテインメント化、世界的にポピュラリティを持って広まることを志向した作品では、個人のクリエイティビティはどうしても薄まってしまいます。だからうちとしては、今後もクリエイター自身の命の輝きのようなものを感じられる丁寧な作品作りを、これまでと同じくやっていくだけです。そういう作品があるほうが面白いし、業界全体の可能性も広がるじゃないですか」
何気ない話題をきっかけに、業界内の自社のポジションに対する自負や誇りをにじませる。それはこれまでに作ってきたアニメへの自信の表れだ。
「だって自分たちが好きな作品ばかり30年以上作ってきたけど、STUDIO4℃は生き長らえてきたんですよ。やっぱり、クリエイターの『これを作りたい』という思いの発露から生まれてくるものを感じられる作品作りをする会社は、業界にとってなくてはならないんです。そういう会社が1つくらいないと偏った世界になってしまう。そこに私たちがいる価値があるというか。だって、STUDIO4℃がなかった30年を想像してみてください。うちの作品は『STUDIO4℃があってよかった』と思えるような価値のあるものばかりでしょう?」
田中栄子(タナカエイコ)
群馬県出身。青山学院大学卒業後、広告代理店勤務。日本アニメーションで制作を務めたのち、スタジオジブリで「となりのトトロ」「魔女の宅急便」のラインプロデューサーを担当。1993年にSTUDIO4℃を設立。「MEMORIES」「アリーテ姫」「マインド・ゲーム」「鉄コン筋クリート」「ベルセルク黄金時代篇」「海獣の子供」など、さまざまな作品の企画・プロデュースを手がける。
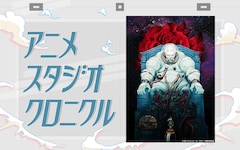


 舞
舞 舞
舞